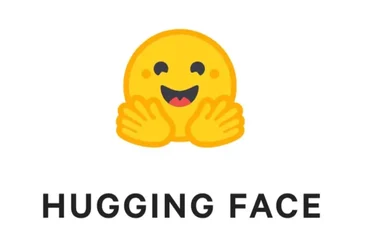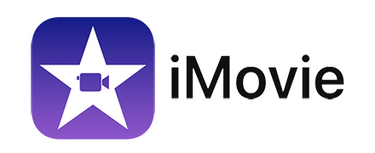カスタマーセンターや社内ヘルプデスク、ECサイトなど様々な場面で活躍を見せているAIチャットボット。そんなAIチャットボットがどのような仕組みになっているのか、気になったことがある方も多いのではないでしょうか。今回は、チャットボットの仕組みや機能について徹底解説していきます。まず、AIチャットボットの仕組みについて解説します。
AIチャットボットの仕組み
まず、AIチャットボットの仕組みについて手順に沿って解説します。
キーワードを抽出
チャットボットはまず、ユーザーの質問文を分析し、重要となるキーワードを抽出します。これはユーザーが何を知りたいのかを正しく汲み取るために重要なステップであり、分析が正しくできていないと的外れな回答をしてしまうことになりかねません。
データベースから答えを導き出す
次に、キーワードから汲み取った「ユーザーの意図」を元に、データベースからユーザーの求める答えを導き出します。データベースの充実度は、より的確な回答を提供するために非常に重要な要素となります。なるべく詳細に設定しておくことで、ユーザーの求める回答ができる確率が高くなります。
また、AI搭載型のチャットボットであれば、過去のユーザーとの会話から学習し、データベースを増築していくことも可能です。
返答する
次に、データベースから導き出した回答を、ユーザーからの質問に対し自然な形で返答します。基本的には、登録されている回答文の中から適切なものを選択して回答する仕組みになっています。そのためチャットボットの運営者は、ユーザーの質問に回答する際の定型文を、できるだけたくさん登録しておく必要があります。
また、AI型チャットボットの場合は、単語一つ一つの要素を組み合わせながら回答文を生成していく機能を備えているものもあります。この機能がある場合、ユーザーの質問に対してより自然な回答を用意できる可能性が高まります。
AIチャットボットの機能
現在、さまざまな特徴を持つチャットボットが販売されており、それぞれ機能も大きく異なります。ここからは、チャットボットで特に注目の機能についてみていきましょう。
自動応答
多くの企業で重宝されているのが、問い合わせ対応を自動化できる、自動応答機能です。AI搭載型のチャットボットであれば、データを蓄積させていくことでAIが学習していくため、問い合わせの回数が増えれば増えるほど自動応答の精度が高まっていくという魅力もあります。
有人対応
AI搭載型のチャットボットでも、複雑な内容の問い合わせには回答しきれないこともちろんあります。そのため、最近では。「チャットボットでは回答できない問い合わせはオペレーター対応に切り替える体制」を構築している企業も多くなっています。こうすることで、オペレーターの負担を軽減しつつも、スムーズな顧客対応を行うことができるのです。
FAQとの連携
オペレーターの負担を軽減させるため、FAQと連携させるチャットボットも多くなってきています。よくある質問に関してはFAQを用意しておくことで、スムーズに対応することができ、オペレーターの負担が減るだけでなく、ユーザーもすばやく疑問を解決することができます。
外部システムとの連携
外部システムと連携できる機能を搭載したチャットボットも増えてきています。たとえば、「予約」と入力すると、そのまま外部の予約システムと連携できるチャットボットなどがあります。外部システムとの連携を柔軟にできるようになれば、チャットボットが集客の窓口としても活躍することになるため、成果にも直結していく可能性があるでしょう。
最後に
今回は、AIチャットボットの仕組みや機能について徹底解説していきました。AIチャットボットは、今後さらに多くの分野で導入されていくことが予想されています。世界で話題になっているAIイメージ生成なども含め、AIチャットボットを活用し、業務効率を改善することで、より多くの人の負担が減っていくことを期待したいですね。